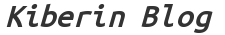必要な手続きがあれば知りたいです。
こんにちは、キベリンブログです。
毎月の給料から引かれる住民税は、退職や転職をするとき、どうすればいいか分かりにくいですよね。
今回は、「住民税の退職後・転職後の手続きと支払方法」を解説します。
【本記事の内容】
① 住民税は、去年の所得から決まる【仕組みと基本ルールを解説】
② 退職時の住民税の手続きには、何が必要?【転職先の有無で変わる】
③ 住民税の減免・軽減制度は受けられる?【市区町村で違う】
④ 住民税は、1年遅れの後払いであることを忘れずに【失業保険にも注意】
会社を退職してすぐ転職する場合と、無職になる場合ともに経験してきました。
本記事を読めば、「3分ほど」で住民税の手続きと、納付方法が分かりますよ。
① 住民税は、去年の所得から決まる【仕組みと基本ルールを解説】

① 住民税は、去年の所得から決まる【仕組みと基本ルールを解説】
まず、住民税の仕組みと基本ルールを解説していきますね。
【住民税の仕組みと基本ルール】
・住民税の金額 : 去年の所得額に応じて決まる(1年遅れの後払い方式)
・支払いの期間 : 「6月から翌年5月」を1年とし、分割して納付
・納付方法 : 「特別徴収(給料から引かれる)」と「普通徴収(自分で支払う)」の2通り
住民税の金額:去年の所得額に応じて決まる(1年遅れの後払い方式)
住民税の金額は、「去年の所得」に応じて決まる「後払い」で、1年後に支払います。
新卒の社会人の2年目は、1年目よりも給料(手取り額)が下がると言われるのは、住民税が引かれるからですね。
支払いの期間:「6月から翌年5月」を1年とし、分割して納付
去年の所得額から決まった住民税を、「当年6月から翌年5月」を1年として「毎月」or「4期に分割」して納付します。
「毎月」か「4期に分割」になるかは、次で説明する納付方法で異なります。
納付方法:「特別徴収(給料から引かれる)」と「普通徴収(自分で支払う)」の2通り
・特別徴収 : 会社員の納付方法で、毎月の給料から引かれる
・普通徴収 : 退職者や個人事業主の納付方法で、4期に分割(6月、8月、10月、1月)して自分で支払う
自分で支払う普通徴収は、「役所から自宅に送られてくる納付書」を使って支払います。
最近では、スマホ決済やクレジットカードで払えたりするので、便利ですね。
住民税で押さえておきたいポイントは、次の内容です。
住民税は1年後の後払いなので、会社を辞めた後に支払う必要がある
退職して無職になったとしても、住民税はかなりの額を支払う必要があるので、しっかり準備しておきましょう。
-

-
住民税のお得な支払い方法とは【スマホ+クレカ】
お悩み相談住民税をコンビニで払うと、クレジットカードが使えなくて不便...。 金額も大きくて現金下ろすの面倒だし、お得で便利な払い方を知りたいな。 こんにちは、キベリンブロ ...
続きを見る
② 退職時の住民税の手続きには、何が必要?【転職先の有無で変わる】

② 退職時の住民税の手続きには、何が必要?【転職先の有無で変わる】
次に、会社を退職する場合の住民税の手続きを見ていきましょう。
転職先が決まっている場合(無職期間のブランクがない場合)
転職先が決まっている場合は、転職先でも引き続き「特別徴収(給料から引かれる)」で納付できます。
次の2点を確認して、手続きを行いましょう。
【転職前後で会社に確認する内容】
・事前に転職先の会社へ、「特別徴収(給料から引かれる)」が可能かを確認しておく
・退職する会社に、「特別徴収(給料から引かれる)」の継続手続きを依頼する
これで、転職先の会社と退職する会社の間で手続きを取ってくれます。
ただし、状況によっては手続きが間に合わない場合もあります。
そのときは、以下のような手順になりますが、特に問題ありません。
【特別徴収の手続きが間に合わなかった場合の手順】
・退職する会社が「普通徴収(自分で支払う)」へ切り替えの手続きをするので、後日に送られてくる納付書で支払う
・その後、転職先の会社で「特別徴収(給料から引かれる)」へ切替手続きを行う
転職先が決まっていない場合
退職する会社が、「普通徴収(自分で支払う)」へ切り替える手続きを行います。
切り替えの手続きは、特に何も言わなくても会社がやってくれるので、忘れても大丈夫です。
退職後、市区町村から住民税の納付書が送られてくるので、その納付書で支払います。
繰り返しですが、住民税はかなりの額を支払う必要があるので、心づもりをしておきましょう。
【退職する月の給料から、住民税がまとめて引かれる場合もある】
先ほど納付書を使って支払うと書きましたが、退職月の給料からまとめて引かれる場合もあります。
退職する月が「1月から5月」のときにこのケースになる場合が多いです。
ですが、決まっているわけではありません。
住民税の額はけっこう大きいので、まとめて引かれると退職月の給料はかなり減ることになります...。
それが厳しいなら、納付書で自分で支払うこともできるので、会社に相談してみましょう。
③ 住民税の減免・軽減制度は受けられる?【市区町村で違う】

③ 住民税の減免・軽減制度は受けられる?【市区町村で違う】
「無職になったから住民税の支払いが厳しい...。」という状況もありますよね。
そこで確認しておきたいのが、住民税の「減免制度(軽減制度)」です。
住民税の減免制度は各市区町村で異なるので、自分の市区町村で調べる必要があります。
ただし、住民税は減免を受けるにはハードルが高いです。
参考例として、東京都品川区の減免制度を受けられる条件を見てみます。
会社を退職しただけではダメで、それなりの理由がないと減免は受けられませんが、確認しておくと良いと思います。
支払いが厳しい場合は、上記以外の理由でも、市区町村の窓口で相談を受け付けています。
※【補足】「国民年金」は免除制度を利用でき、「健康保険」は退職理由によって軽減制度を利用できます。
詳細は、「【国民年金】退職したら保険料の免除制度を利用しよう」と「【健康保険】退職後の保険料の軽減制度」にて解説しています。
④ 住民税は、1年遅れの後払いであることを忘れずに【失業保険にも注意】

④ 住民税は、1年遅れの後払いであることを忘れずに【失業保険にも注意】
本記事では、「住民税の退職後・転職後の手続きと支払方法」を解説しました。
ポイントをまとめます。
【住民税の仕組みと基本ルール】
・住民税の金額 : 去年の所得額に応じて決まる(1年遅れの後払い方式)
・支払いの期間 : 「6月から翌年5月」を1年とし、分割して納付
・納付方法 : 「特別徴収(給料から引かれる)」と「普通徴収(自分で支払う)」の2通り
【退職時の住民税の手続き(転職先が決まっている場合)】
・事前に転職先の会社へ、「特別徴収(給料から引かれる)」が可能かを確認しておく
・退職する会社に、「特別徴収(給料から引かれる)」の継続手続きを依頼する
【退職時の住民税の手続き(転職先が決まっていない場合)】
・退職する会社が「普通徴収(自分で支払う)」へ切り替えるので、後日に市区町村から送られてくる納付書で自分で支払う
(※退職月の給料からまとめて引かれる場合は不要)
すぐに転職しない場合、退職後の収入のない状態での住民税の支払いは、けっこう負担が大きいです。
失業保険がもらえるので、それで支払えるとも言えますが、しっかりと心づもりはしておきましょう。
-

-
国民健康保険料のお得な支払い方法【eL-QR対応】
お悩み相談健康保険料の支払いって、ラクでお得な払い方あるのかな? コンビニ払いはクレジットカード使えないし、金額も大きくて現金は面倒...。 こんにちは、キベリンブログです ...
続きを見る
-

-
【国民年金】スマホ決済が可能に【お得な支払い方法】
お悩み相談住民税とかスマホ決済で払えるようになってきたけど、国民年金もスマホアプリで払えるの?? こんにちは、キベリンブログです。 国民年金保険料も、スマホ決済アプリで支払 ...
続きを見る