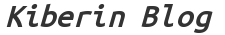保険料っていくらなんだろう??
こんにちは、キベリンブログです。
会社を辞めると収入も減るし、保険料がいくらになるか知らないと不安ですよね。
今回は、「退職後の国民健康保険料の目安と、安くする2つの方法」について紹介します。
【本記事の内容】
① 退職して無職になるときの国民健康保険料の目安【去年の収入】
② 健康保険料を安くする、2つの方法とは【軽減措置と任意継続】
③ まとめ:収入がなくても健康保険料はかかるので、退職前に知っておくと安心
健康保険料は、思った以上に高くつくことが多いです。
退職経験から、安くする方法にも触れていきますね。
① 退職して無職になるときの国民健康保険料の目安【去年の収入】

① 退職して無職になるときの国民健康保険料の目安【去年の収入】
国民健康保険料は、退職して無職になっても支払わなければなりません。
保険料の金額は「前年の収入」から計算されます。
収入が高いほど、保険料も高くなる仕組みですね。
要するに、その時点で収入がゼロでも、それなりの金額が必要になってきます。
国民健康保険料の目安【年収別】
健康保険料は、市区町村によって違いがあります。
なので正確な金額を調べようとすると、「所得割」や「均等割」とか出てきたりして難しいんですよね。
多少のずれはあっても、簡単にわかる目安の金額は知っておきたいと感じていました。
そこで前年の年収別での 東京都新宿区 の保険料(令和6年度分)を、「単身者」の例で紹介していきます。
【東京都新宿区の国民健康保険料(※単身者で1か月あたり)】
| 前年の年収 | 40~64歳以外 | 40~64歳 |
| 年収100万 | 5,658円 | 7,069円 |
| 年収200万 | 13,988円 | 16,965円 |
| 年収300万 | 20,691円 | 24,928円 |
| 年収400万 | 27,776円 | 33,345円 |
| 年収500万 | 35,436円 | 42,445円 |
| 年収700万 | 51,139円 | 61,100円 |
| 年収1000万 | 73,322円 | 87,488円 |
去年の年収が500万円の場合、無職でも年間で約42万円以上はかかる
新宿区の例で、去年の年収が500万の場合の保険料を年間に換算してみましょう。
1年間で40~64歳以外は「約42万円」、40~64歳は「約51万円」ほどかかります。
無職で収入がなかったとしても、この金額を払わなければならないんですよね。
かなり大きな負担になるはずです。
事前に知っておかないと準備が難しいこともあるので、注意しておいてくださいね。
② 健康保険料を安くする、2つの方法とは【軽減措置と任意継続】

② 健康保険料を安くする、2つの方法とは【軽減措置と任意継続】
繰り返しですが、健康保険料は「前年の収入」にかかるので、退職した後だと負担を感じやすいです。
無職で収入がなかったりすると、なおさらですよね。
そこで、健康保険料を安くできる可能性があります。
その方法を紹介していきますね。
【健康保険料を安くする方法】
❶ 国民健康保険料の軽減制度を使う
❷ 任意継続(退職した会社の健康保険)に加入する
❶ 国民健康保険料の軽減制度を使う
国保(国民健康保険)には「軽減制度」があります。
ただ申請条件があり、退職理由によって申請できるかが決まってきます。
【国民健康保険料の軽減制度の申請条件(非自発的失業)】
・会社都合退職 : 解雇や倒産、派遣契約終了後に次の仕事が紹介されなかった場合など
・正当な理由のある自己都合退職 : 身体の問題や家族看護、通勤が困難な場合など
上記のどちらかの退職理由なら、軽減制度を申請できます。
「所得を総額の30%」として保険料を計算するので、かなり減免されますね。
例えば、前年の年収が300万円だった場合、年間で「約20万円」は安くなります。
これだけ安くできたら、かなり大きいですよね。
※軽減制度の手続きなど詳しい内容は、「【健康保険】退職後の保険料の軽減制度とは?【退職理由が重要】」をご覧ください。
❷ 任意継続(退職した会社の健康保険)に加入する
退職して無職になったときの健康保険は、実は国保以外にも選択肢があります。
「任意継続」と呼ばれていますが、「退職した会社の健康保険」に引き続き加入する方法です。
ただし保険料は、働いていたときと同じではありません。
なぜなら会社が半額を負担してくれていたので、任意継続だと2倍に増えます。
2倍と聞くと国保よりも高いと思うかもしれませんが、そうでもなかったりするんですよね。
任意継続のポイントとしては、以下のとおりです。
【任意継続のポイント】
・国民健康保険とは保険料が異なるので、比べて検討する
・目安の分岐点は年収500万で、年収が高いほど任意継続の方が安くなる
・加入できる期間は、退職から最大2年まで
任意継続は2022年から法改正によって、好きなときに脱退できるよう変わっています。
以前よりも選びやすくなり、「退職から1年間だけ任意継続を選ぶ」といったお得になるテクニックも使えますよ。
※任意継続の詳しい内容は、「【退職後】任意継続と国民健康保険はどっちが安い?【比較と選び方】」で解説しています。
③ まとめ:収入がなくても健康保険料はかかるので、退職前に知っておくと安心

③ まとめ:収入がなくても健康保険料はかかるので、退職前に知っておくと安心
本記事では、「退職後の国民健康保険料の目安と、安くする2つの方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【東京都新宿区の国民健康保険料(※単身者で1か月あたり)】
| 前年の年収 | 40~64歳以外 | 40~64歳 |
| 年収100万 | 5,658円 | 7,069円 |
| 年収200万 | 13,988円 | 16,965円 |
| 年収300万 | 20,691円 | 24,928円 |
| 年収400万 | 27,776円 | 33,345円 |
| 年収500万 | 35,436円 | 42,445円 |
| 年収700万 | 51,139円 | 61,100円 |
| 年収1000万 | 73,322円 | 87,488円 |
【健康保険料を安くする方法】
❶ 国民健康保険料の軽減制度を使う
❷ 任意継続(退職した会社の健康保険)に加入する
退職後の社会保険料は、意外と高くつくことが多いです。
特に国民健康保険料は、一律で同じ金額の国民年金と違って、金額がわかりにくい仕組みになっています。
1年で「何十万」もかかったりするので、辞めてから「無職でもこんなに高いの!?」ということを知ったりするんですよね。
目安だけでも、事前に知っておくと安心です。
軽減制度や任意継続を活用できれば、条件次第で安くなります。
ぜひ本記事を参考に、健康保険料のポイントを押さえておいてくださいね。
-

-
国民健康保険料のお得な支払い方法【eL-QR対応】
お悩み相談健康保険料の支払いって、ラクでお得な払い方あるのかな? コンビニ払いはクレジットカード使えないし、金額も大きくて現金は面倒...。 こんにちは、キベリンブログです ...
続きを見る
-

-
【退職後】任意継続と国民健康保険はどっちが安い?【比較と選び方】
お悩み相談会社を辞めた後の健康保険は、任意継続と国民健康保険のどっちを選ぶとお得なのかな?? こんにちは、キベリンブログです。 任意継続と国保(国民健康保険)は保険料が違い ...
続きを見る
-

-
【国民年金】スマホ決済が可能に【お得な支払い方法】
お悩み相談住民税とかスマホ決済で払えるようになってきたけど、国民年金もスマホアプリで払えるの?? こんにちは、キベリンブログです。 国民年金保険料も、スマホ決済アプリで支払 ...
続きを見る