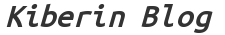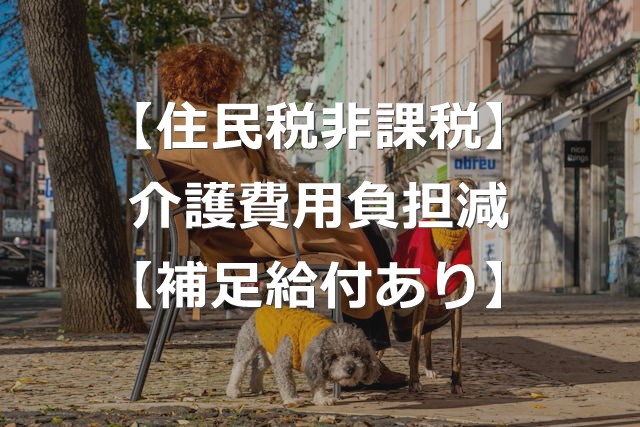え、費用の負担が軽くなる補足給付があるの!?
こんにちは、キベリンブログです。
介護の問題は避けられないので、かかる費用は気になりますよね。
今回は、「特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象者と、負担上限額のしくみ」について紹介します。
【本記事の内容】
① 特定入所者介護サービス費(補足給付)とは【対象者と負担額】
② 低所得の年金受給者には、年金生活者支援給付金がもらえる【6.5万円】
③ まとめ:老人ホームや介護施設利用時は、補足給付の対象か要チェック
税金・社会保険は、知らないままでいると損することになります。
活かせる制度のしくみを、わかりやすく語っていきます。
① 特定入所者介護サービス費(補足給付)とは【対象者と負担額】
とは【対象者と負担額】.jpg)
① 特定入所者介護サービス費(補足給付)とは【対象者と負担額】
介護保険施設に入った場合、居住費と食費については "介護保険の対象外" となります。
つまり、利用者が「全額自己負担」しなければなりません。
もらえる年金が少なかったり、預貯金などの資産がない人にとっては、支払いが厳しくなってしまいます。
そこで所得や貯金が少ない人向けに、「補足給付(特定入所者介護サービス費)」を受けられる制度があります。
自己負担の上限額が決められているしくみで、上限を超えた分は補足給付として介護保険から支払われます。
どんな人が補足給付の対象となるのか、具体的にチェックしていきましょう。
補足給付の対象者【※住民税非課税世帯であることが前提】
| 負担段階 | 対象者 | 預貯金額(単身・夫婦) |
| 第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
| 第2段階 | 年金収入+合計所得:80万円以下 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階① | 年金収入+合計所得:80万円~120万円 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階② | 年金収入+合計所得:120万円超 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
補足給付の対象となるには、「住民税非課税世帯」であることが前提条件です。
その上で、上の表に記載されている一定の所得条件と、預貯金額を満たす必要があります。
負担段階は第3段階まで分かれており、上の段階になるほど、受けられる補足給付の金額は大きくなります。
つまり、上の段階の方が自己負担限度額が低く抑えられているということですね。
例えば、第2段階の対象者になるには、年金収入+その他の所得の合計が「80万円以下」で、かつ預貯金が「1,000万円以下(夫婦世帯なら2,000万円以下)」であればOKです。
なお、年金収入はもらった金額をそのまま足せばOKですが、その他の所得は「収入 - 控除(経費)」で計算するので、注意しておきましょう。
-

-
年金収入で住民税非課税世帯になる年収条件【+給与・副業収入時】
お悩み相談住民税非課税世帯になると給付金がもらえる対象になるよね。 年金受給者は、どのくらいの年収だと非課税になるの? こんにちは、キベリンブログです。 年金収入の場合、給 ...
続きを見る
居住費の自己負担限度額(※月額あたり)
| 居住種類 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①・② |
| 多床室(特養・老健・医療院) | 0円 | 1.3万円 | 1.3万円 |
| 従来型個室(特養) | 1.1万円 | 1.4万円 | 2.6万円 |
| 従来型個室(老健・医療院) | 1.7万円 | 1.7万円 | 4.1万円 |
| ユニット型多床室 | 1.7万円 | 1.7万円 | 4.1万円 |
| ユニット型個室 | 2.6万円 | 2.6万円 | 4.1万円 |
居住費における自己負担限度額は、入っている介護施設と段階によって、上記のとおり決められています。
例えば、第2段階の人が「ユニット型個室」を利用していた場合の居住費は、最大でも月額では約2.6万円の自己負担で済みます。
その上限額を超えた分の費用については、補足給付として支払われるということですね。
(実際の費用は1日あたりで計算される)
食費の自己負担限度額(※月額あたり)
| 居住種類 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
| 施設サービス | 0.9万円 | 1.2万円 | 2.0万円 | 4.1万円 |
| ショートステイ | 0.9万円 | 1.8万円 | 3.0万円 | 3.9万円 |
食費における自己負担限度額は、上記のとおりです。
こちらも居住費と同様、利用している居住種類と段階によって自己負担額が変わるしくみです。
例えば、第2段階の人が「ショートステイ」を利用した場合での食費は、最大でも月額では約1.8万円の自己負担で済みます。
(実際の費用は1日あたりで計算される)
② 低所得の年金受給者には、年金生活者支援給付金がもらえる【6.5万円】

② 低所得の年金受給者には、年金生活者支援給付金がもらえる【6.5万円】
ここまで、介護施設の利用時に費用負担が軽くなる「補足給付(特定入所者介護サービス費)」を紹介してきました。
住民税非課税世帯であることを前提として、所得や貯金が少ない人が受けられる制度です。
その他にも、所得が少ない人には、"上乗せ" で支給される給付金があります。
知らない限りは給付対象にもならないので、その給付金についても、ここで紹介しておきますね。
所得が少ない人がもらえる、年金生活者支援給付金とは
「年金生活者支援給付金」とは、年金収入を含めても "一定基準より所得が低い人" を支援する給付金制度です。
給付金の対象になると、年金に上乗せして支給されます。
年金生活者支援給付金は、いくらもらえるか【年6.5万円】
・月5,450円(2025年度の支給額)
→ 年間で65,400円
・前年度比で、「+140円(2.7%)」の増額(毎年4月に改定)
年金生活者支援給付金の支給額は、1ヶ月あたり「5,450円(2025年度)」です。
年間で「6.5万円」ですね。(未納期間・免除期間がある場合は減額あり)
なお、支給額は毎年4月に改定されます。
物価変動率を反映して改定され、2025年度は前年度比で2.7%増額になっています。
支給要件を満たしていれば、毎年繰り返し支給されます。
非課税なので、税金はかかりません。
年金生活者支援給付金がもらえる対象者【3つの要件】
要件❶ : 65歳以上で、年金を受給している
要件❷ : 世帯全員が、住民税非課税
要件❸ : 前年の「年金収入+その他の所得」が、88.9万円以下
※3つすべて満たす必要あり
どんな人が6.5万円の上乗せ支給の対象になるかというと、上記の "3要件" をすべて満たす人です。
給付金の名称からも分かるとおり、「年金受給者」であることが前提です。
また、生計を同一にしている世帯全員が、"住民税非課税" でなければなりません。(住民税非課税世帯)
単身者は年金収入が155万円以下だと、住民税非課税となります。
最後の要件である所得の基準ですが、「88.9万円以下」が条件です。
年金収入だけでなく、他の所得も合計した金額なので、合わせてチェックしてみてください。(申請方法は関連記事で解説しています)
-

-
【要申請】年金生活者支援給付金で、6.5万円の上乗せ支給!
お悩み相談年金収入だけだと、物価も上がってるし生活厳しいなぁ...。 え、年金に上乗せでもらえる給付金があるの!? こんにちは、キベリンブログです。 厚生年金の加入期間が短 ...
続きを見る
③ まとめ:老人ホームや介護施設利用時は、補足給付の対象か要チェック

③ まとめ:老人ホームや介護施設利用時は、補足給付の対象か要チェック
本記事では、「特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象者と、負担上限額のしくみ」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【補足給付の対象者(※住民税非課税世帯であることが前提)】
| 負担段階 | 対象者 | 預貯金額(単身・夫婦) |
| 第1段階 | 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
| 第2段階 | 年金収入+合計所得:80万円以下 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階① | 年金収入+合計所得:80万円~120万円 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階② | 年金収入+合計所得:120万円超 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
【居住費の自己負担限度額(※月額あたり)】
| 居住種類 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階①・② |
| 多床室(特養・老健・医療院) | 0円 | 1.3万円 | 1.3万円 |
| 従来型個室(特養) | 1.1万円 | 1.4万円 | 2.6万円 |
| 従来型個室(老健・医療院) | 1.7万円 | 1.7万円 | 4.1万円 |
| ユニット型多床室 | 1.7万円 | 1.7万円 | 4.1万円 |
| ユニット型個室 | 2.6万円 | 2.6万円 | 4.1万円 |
【食費の自己負担限度額(※月額あたり)】
| 居住種類 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
| 施設サービス | 0.9万円 | 1.2万円 | 2.0万円 | 4.1万円 |
| ショートステイ | 0.9万円 | 1.8万円 | 3.0万円 | 3.9万円 |
自身や家族を含め、高齢になれば介護の問題は避けられません。
老人ホームや介護施設に入れば、それなりの費用はかかってしまいます。
年金が少なかったり、預貯金などの資産も少ない人には、「補足給付(特定入所者介護サービス費)」が受けられます。
自己負担限度額を超える分が給付されるので、最大でも限度額までの負担で済みます。
こういった給付金制度は、知らなければ活用できません。
本記事を参考に制度の存在を知って、対象になるかチェックしてみてくださいね。
-
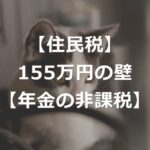
-
年収155万円・211万円の壁とは【年金で住民税非課税世帯に】
お悩み相談 "103万円の壁" とかはよく聞くけど、211万円の壁ってなに?? こんにちは、キベリンブログです。 年収の壁の引き上げが話題ですが、いくつも壁があって分からな ...
続きを見る
-

-
【年金制度改正】加給年金が改悪?変わる支給額と、6つの改正
お悩み相談年金制度改正で、加給年金が変わるんだね。 ・・・加給年金って、なに?? こんにちは、キベリンブログです。 2025年に年金制度改正法が成立して、今後の年金が変わっ ...
続きを見る
-

-
住民税非課税世帯が優遇される、7つのメリット【年収の目安】
お悩み相談"住民税非課税世帯" ってよく聞くけど、どんなメリットがあるの? こんにちは、キベリンブログです。 税金はしくみがややこしくて、非課税のメリットもあまり知られてい ...
続きを見る