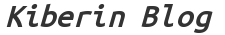扶養に入る年収条件ってどのくらい?
こんにちは、キベリンブログです。
高齢の親を扶養に入れれば保険料負担が減るし、可能なら入れてあげたいですよね。
今回は、「年金受給者が扶養に入れる年収条件と、年金もらいながら働ける範囲」について紹介します。
【本記事の内容】
① 高齢の親を扶養に入れる、メリット・デメリット【健康保険料と税金】
② 年金受給者は、年収いくらまで扶養に入れるか【年金+給与収入】
③ まとめ:高齢の親も健康保険料を払わずに済むので、扶養の条件は要チェック
年収の壁の引き上げもあり、扶養の条件も以前から変わっています。
知っていれば役立つ社会保険の知識を、わかりやすく語っていきます。
① 高齢の親を扶養に入れる、メリット・デメリット【健康保険料と税金】

① 高齢の親を扶養に入れる、メリット・デメリット【健康保険料と税金】
扶養とは、自分で生計を立てられない家族や親族を養うことです。
その分お金がかかるため、社会保険や税金面で優遇される制度があります。
扶養というと、配偶者(妻・夫)や子どもをイメージしますよね。
実は年金で生活している "高齢の親" も、扶養にする対象になります。
扶養に入れるには、親の収入に制限があります。
具体的な収入の話に入る前に、扶養に入れるメリット・デメリットについて簡単に触れておきますね。
高齢の親を、扶養に入れるメリット
・国民健康保険料がかからない【社会保険】
・扶養控除(38~58万円)があり、税金が安くなる【税金】
扶養に入れるメリットとして、「社会保険」と「税金」で優遇措置が受けられます。
社会保険では、親が加入する国民健康保険(75歳まで)について、健康保険料がかからなくなります。
一般的に国民健康保険は会社の健康保険よりも保険料が高い傾向があるので、保険料の負担が軽くなるのは大きいですよね。
もう一方の税金面では、扶養控除が受けられます。
親が70歳未満なら38万円の控除、70歳以上なら48万円(親と同居なら58万円)が控除に。
控除額は課税所得から差し引かれて税金が計算されるので、減税になるということですね。
高齢の親を、扶養に入れるデメリット
・高額療養費制度の自己負担限度額が上がる可能性がある
・収入に制限がある
扶養にはメリットしかないと思われがちですが、実はデメリットも存在します。
医療費に関して、親の高額療養費制度の自己負担額が上がる可能性があります。
高額療養費制度とは、所得に応じて決められた自己負担限度額を超える医療費について、後から超えた分が支給される制度です。
本来は親の所得のみで自己負担額が決まるので安く抑えられますが、扶養に入れると子の所得で決まるので、自己負担額が上がるケースが多いです。
また、扶養の状態を継続するには、"親の収入" を制限しなければなりません。
具体的にいくらまでなら扶養の範囲内で稼げるのか、次のパートで見ていきましょう。
-
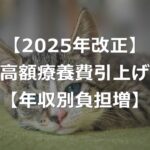
-
【2025改正】高額療養費、3段階の引き上げで負担増【健康保険】
お悩み相談高額療養費制度の上限額が変わるの? 仕組みもよく知らないんだけど、負担が増えるってこと!? こんにちは、キベリンブログです。 健康保険の高額療養費制度が、10年ぶ ...
続きを見る
② 年金受給者は、年収いくらまで扶養に入れるか【年金+給与収入】

② 年金受給者は、年収いくらまで扶養に入れるか【年金+給与収入】
ここまで、高齢の親を扶養に入れるメリット・デメリットを見てきました。
扶養に入れると、「社会保険(健康保険料)」と「税金面(扶養控除)」で優遇され、経済的な負担が軽くなります。
ただし扶養に入れるには、親の収入が基準以下でなければなりません。
「年金収入でいくらまでなら扶養に入れるんだろう?」「年金もらいながらアルバイトしたら扶養に入れるかな?」など、気になったりしますよね。
そこで扶養に入れる年収条件を、具体的な金額で見ていきましょう。
年金収入と給与収入で金額は変わってくるので、参考にしてみてください。
扶養に入れる所得条件【2025年から変更】
・年間の所得が、「58万円以下」であること
(※ 所得 = 収入 - 控除)
親を扶養に入れるには、親の年間の所得額が「58万円以下」であることが条件です。
2024年までは48万円以下でしたが、2025年からは58万円に引き上げられました。
「年収が58万円以下って厳しくない?」と思ったりしますよね。
でも注意が必要なのは、所得は年収のことではありません。
所得とは、「収入から "控除" を引いたもの」なので、年収額としてはもっと多くてもOKです。
控除の額は年金収入と給与収入(アルバイトなどで働いたときの給料)で違うので、それぞれ見ていきます。
年金収入のみで、扶養に入れる年収条件
・年金収入のみの場合、「年収168万円以下」であること(65歳以上)
→ 公的年金等控除が110万円なので、所得58万円以下となる
親が年金収入のみの場合は、「年収168万円以下」なら扶養に入れます。
月額でみたら "14万円以下" となる計算ですね。
国民年金の満額受給で月額7万円ほどなので、年収168万円以下になる人は多いかもしれません。
年金収入で所得を計算する場合、"公的年金等控除(110万円)" というものが適用されます。
年金での年収が168万円以下なら、所得が58万円以下になるという計算ですね。
(65歳未満で繰り上げ受給している場合は、控除額が60万円に下がる)
年金収入+給与収入の場合、いくらまで扶養の範囲で働けるか【合計所得 58万円以内】
・給与収入での控除額(給与所得控除)は、65万円
→ 給料が65万円を超えた分から、所得額にカウントされる
・年金収入が「140万円(所得30万円)」なら、給与収入は「93万円(所得28万円)」まで働ける
年金をもらいながらアルバイトなどで働いた場合は、適用される控除が変わります。
給与収入の場合、"給与所得控除(65万円)" というものが適用されます。
働いて稼いだ給料から65万円分が差し引かれるので、所得額としては65万円を超えた分からカウントされます。
年金収入での控除額(110万円)よりも少ないので、その点は注意が必要ですね。
例えば、年金収入が140万円なら所得は30万円なので、給与収入での所得を48万円以内にすれば、扶養の範囲内で働けます。
つまり、「年金収入140万円(所得30万円)+給与収入93万円(所得28万円)= 年収233万円(所得58万円)」となり、給与収入で "93万円までパートやアルバイトで働ける" という計算になります。
-

-
年金収入で住民税非課税世帯になる年収条件【+給与・副業収入時】
お悩み相談住民税非課税世帯になると給付金がもらえる対象になるよね。 年金受給者は、どのくらいの年収だと非課税になるの? こんにちは、キベリンブログです。 年金収入の場合、給 ...
続きを見る
③ まとめ:高齢の親も健康保険料を払わずに済むので、扶養の条件は要チェック

③ まとめ:高齢の親も健康保険料を払わずに済むので、扶養の条件は要チェック
本記事では、「年金受給者が扶養に入れる年収条件と、年金もらいながら働ける範囲」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【扶養に入れる所得条件(2025年から変更)】
・年間の所得が、「58万円以下」であること
(※ 所得 = 収入 - 控除)
【年金収入のみで、扶養に入れる年収条件】
・年金収入のみの場合、「年収168万円以下」であること(65歳以上)
→ 公的年金等控除が110万円なので、所得58万円以下となる
【年金収入+給与収入の場合、いくらまで扶養の範囲で働けるか(合計所得 58万円以内)】
・給与収入での控除額(給与所得控除)は、65万円
→ 給料が65万円を超えた分から、所得額にカウントされる
・年金収入が「140万円(所得30万円)」なら、給与収入は「93万円(所得28万円)」まで働ける
高齢の親を扶養に入れると、社会保険と税金面で優遇措置が受けられます。
親の健康保険料がかからなくなり、扶養控除で税金の負担が軽くなるメリットがあります。
ただし、扶養の状態を維持するには、親の年収が基準以下でなければなりません。
年金収入のみであれば、「年収168万円以下」で扶養に入れます。
年金をもらいながらアルバイトなどで働く場合は、年金と給与収入の合計所得を「58万円以下」にすればOKです。
年金収入の控除額は110万円、給与収入の控除額は65万円を差し引けるので、あなたの収入に合わせて計算してみてくださいね。
-
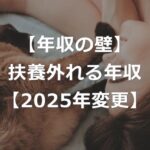
-
【税金・社会保険】扶養から外れる年収123万円の壁【2025年改正】
お悩み相談扶養控除の対象になるのって、年収103万円じゃなかったっけ? 2025年から変わったの?? こんにちは、キベリンブログです。 2025年は税制改正があり、年収の壁 ...
続きを見る
-

-
【2026年4月】独身税が徴収開始!独身以外も払う年収別負担額
お悩み相談独身税が始まるって聞いたけど、本当にそんな税金取られるの?? こんにちは、キベリンブログです。 "独身税" は通称ですが、実際のところ新たな負担がまた増えます。 ...
続きを見る
-
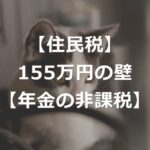
-
年収155万円・211万円の壁とは【年金で住民税非課税世帯に】
お悩み相談 "103万円の壁" とかはよく聞くけど、211万円の壁ってなに?? こんにちは、キベリンブログです。 年収の壁の引き上げが話題ですが、いくつも壁があって分からな ...
続きを見る