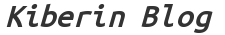こんにちは、キベリンブログです。
"独身税" は通称ですが、実際のところ新たな負担がまた増えます。
今回は、「2026年4月からの "独身税" と、年収別での負担額」について紹介します。
【本記事の内容】
① 2026年4月から徴収される "独身税"、健康保険料に上乗せで徴収【年収別の負担額】
② 払った子ども・子育て支援金は、何に使われるのか【4つの使い道】
③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は、独身だけでなく健康保険加入者が払う
税金・社会保険料は増える一方で、少子高齢化が加速する時代に軽くなることはありません。
独身税の中身について、わかりやすく紹介していきます。
① 2026年4月から徴収される "独身税"、健康保険料に上乗せで徴収【年収別の負担額】

① 2026年4月から徴収される 独身税、健康保険料に上乗せで徴収【年収別の負担額】
2026年4月から、"独身税" が徴収されます。
「独身の人だけが対象になるの!?」と思ってしまいますよね。
でも実際の中身をみると、そうではありません。
誰が・いつから・どうやって負担するかのしくみなど、詳しく見ていきましょう。
独身税の正式名称は、"子ども・子育て支援金"【2026年4月から徴収】
独身税というのは俗称で、そういう名前の税金はありません。
正式には、「子ども・子育て支援金」という制度です。
この制度が設けられた背景は、少子化対策のために作られたものです。
子育て支援の財源にするために、徴収されるということですね。
子どもがいない人にも負担が発生し、直接的なリターンを受けられないことから、独身税という名前が広がりました。
負担するのは、独身の人だけではない【健康保険料に上乗せ】
通称で "独身税" と呼ばれる「子ども・子育て支援金」は、独身の人だけが負担するわけではありません。
社会保険である "健康保険料に上乗せされる" しくみなので、「健康保険に加入している人」が子ども・子育て支援金(独身税)を払うことになります。
健康保険とは、市区町村の「国民健康保険」と、会社員や公務員が加入する「健康保険」が対象になります。
日本は国民皆保険制度のため、多くの人が子ども・子育て支援金(独身税)を負担するということですね。
ここで気になるのは、「いったいいくら取られるの!?」ということですよね。
年収や時期に応じて負担額が変わってくるので、年収別での試算額を見ていきましょう。
子ども・子育て支援金(独身税)の年収別での負担額【年額】
| 年収 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
| 200万円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,200円 |
| 400万円 | 4,800円 | 6,600円 | 7,800円 |
| 600万円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 |
| 800万円 | 9,600円 | 12,600円 | 16,200円 |
| 1000万円 | 12,000円 | 16,200円 | 19,800円 |
政府の「こども家庭庁」が公表した年収別での試算額は、上の表のとおりです。
年収が高いほど、負担額も増えるしくみになっています。
「2026年度(4月~翌年3月)」から徴収が始まり、2026年、2027年、2028年と段階的に負担額が増えていきます。
28年度には、徴収総額を1兆円とする予定です。
増額の幅は、2026年から2028年の2年間で、"2倍弱" にも。
少しずつコソッと増やしていくやり方は、気分のいいものではないですよね。
払いたくなくても、払う必要あり?【無職でも負担】
繰り返しですが、子ども・子育て支援金(独身税)は、健康保険料に上乗せされます。
払いたくなくても健康保険に加入している限り、支払わなければなりません。
たとえ収入のない無職の人や、75歳以上の年金収入だけの後期高齢者も、負担することになっています。
(※国民健康保険料は無職で収入がなくても、健康保険料がかかります)
-

-
【退職後】無職の国民健康保険料はいくら?【年収別+安くする方法】
お悩み相談会社を退職したら無職だけど、国民健康保険に入るんだよね。 保険料っていくらなんだろう?? こんにちは、キベリンブログです。 会社を辞めると収入も減るし、保険料がい ...
続きを見る
② 払った子ども・子育て支援金は、何に使われるのか【4つの使い道】

② 払った子ども・子育て支援金は、何に使われるのか【4つの使い道】
ここまで、独身税と呼ばれる「子ども・子育て支援金」について見てきました。
負担するからには、「いったい何に使うの?」ということも気になりますよね。
子育て支援金の使い道は、4つに限定されています。
支給対象になるのかも含めて、参考にしてみてください。
【子ども・子育て支援金(独身税)の使い道】
❶ 出産応援交付金(10万円)
❷ 児童手当の拡充
❸ 育児休業給付の引き上げ
❹ こども誰でも通園制度
❶ 出産応援交付金(10万円)
・妊産婦に10万円相当を支給する制度
・所得などの制限なし
1つ目は、出産応援交付金です。
いわゆる出産手当で、所得などの制限なく「10万円」が支給されます。
❷ 児童手当の拡充
・高校生まで延長
・所得制限を撤廃
・第3子以降、毎月3万円
2つ目は、児童手当の拡充です。
以前の児童手当は、「3歳未満:月1.5万円」、「3歳~中学生:月1万円」でした。
それが児童手当の拡充により、「中学生まで → 高校生まで」に延長されています。
所得制限は撤廃され、高所得でも児童手当の減額や支給対象外のケースはなくなることに。
また、第3子以降は「毎月3万円」に増額となっています。
ただし、第3子としてのカウントは「支給対象となる高校生までの子どもが3人」という仕組みであり、1人目が高校を卒業すると "2人目" として扱われるので注意が必要です。
❸ 育児休業給付の引き上げ
・育休期間中の給料を、手取りで実質10割にする
・男性の育休取得率を向上させる狙い
3つ目は、育児休業給付の引き上げです。
これまでの育児休業給付金は、給料の67%です。
育休中は社会保険料が免除されるため、手取りでは "8割" になるよう設定されていました。
それが引き上げによって、手取りで「実質10割」となるようにしています。
❹ こども誰でも通園制度
・親の就労要件を問わず、保育所などを利用できる
・毎月の時間単位で、柔軟に預けられるしくみ
4つ目は、こども誰でも通園制度です。
これまでの保育施設の利用は、就労していることなどが条件です。
就労要件や働き方を問わず、誰でも保育所を利用できるよう条件を緩和します。
利用方法も柔軟にし、定期利用や自由利用など、時間単位で利用できるよう検討しています。
-
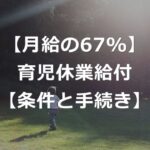
-
【月給67%】育児休業給付金の条件と申請方法【失業給付から分離】
お悩み相談育児休業給付って、「失業等給付」の枠から分離したんだね。 受給する条件や申請方法は変わったのかな? こんにちは、キベリンブログです。 育児休業給付は、2020年4 ...
続きを見る
③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は、独身だけでなく健康保険加入者が払う
は、独身だけでなく健康保険加入者が払う.jpg)
③ まとめ:独身税(子ども・子育て支援金)は、独身だけでなく健康保険加入者が払う
本記事では、「2026年4月からの "独身税" と、年収別での負担額」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【2026年4月から徴収される、"独身税" とは】
・独身税は通称で、正式には「子ども・子育て支援金」という制度
・独身の人だけでなく、健康保険加入者が健康保険料に上乗せで徴収される
・負担額は年収に応じて決まり、2028年度まで段階的に増えていく
【子ども・子育て支援金(独身税)の年収別での負担額】
| 年収 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 |
| 200万円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,200円 |
| 400万円 | 4,800円 | 6,600円 | 7,800円 |
| 600万円 | 7,200円 | 9,600円 | 12,000円 |
| 800万円 | 9,600円 | 12,600円 | 16,200円 |
| 1000万円 | 12,000円 | 16,200円 | 19,800円 |
【子育て支援金の使い道】
❶ 出産応援交付金(10万円)
❷ 児童手当の拡充
❸ 育児休業給付の引き上げ
❹ こども誰でも通園制度
"独身税" と呼ばれる「子ども・子育て支援金」は、2026年4月から徴収が始まります。
健康保険料に上乗せして請求されるので、独身の人だけが負担するわけではなく、健康保険の加入者は負担しなければなりません。
実質的に "増税" ですね。
たとえ収入のない「無職」でも国民健康保険料はかかるので、子ども・子育て支援金は払うことになります。
2026年度から2028年度までは、段階的に負担額が増えていきます。
月給から天引きされる税金・社会保険料は増える一方なので、手取り額には注意してくださいね。
-

-
【2025年改正】住民税非課税の年収条件が引き上げ【110万円の壁】
お悩み相談2025年から、住民税非課税世帯になる年収の条件が変わってるの? こんにちは、キベリンブログです。 2025年から "年収の壁" が変わり、住民税非課税世帯の年収 ...
続きを見る
-
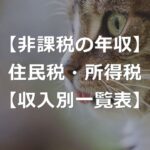
-
【住民税・所得税】新たに変わった年収非課税枠【給与・事業・年金】
お悩み相談年収って、いくらまでなら税金かからないんだっけ? 103万円の壁とか、今はもう変わっているの?? こんにちは、キベリンブログです。 2025年以降、年収の非課税枠 ...
続きを見る
-

-
【社会保険】2026年に"106万円の壁"撤廃へ【新たな壁】
お悩み相談年収106万円の壁、いつ撤廃になるのか決まったの? 撤廃っていっても、手取りが増えるわけじゃないよね?? こんにちは、キベリンブログです。 106万円の壁の撤廃案 ...
続きを見る