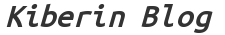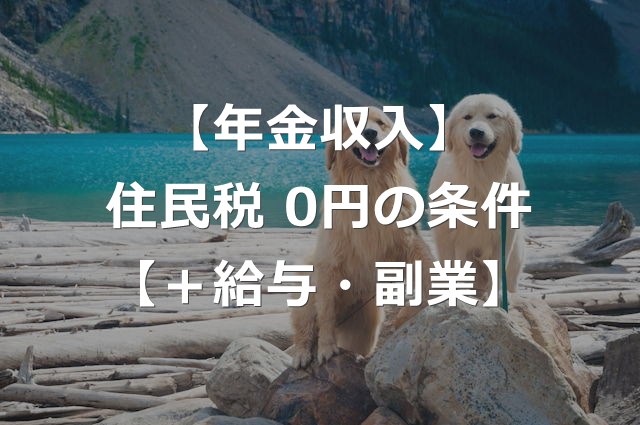年金受給者は、どのくらいの年収だと非課税になるの?
こんにちは、キベリンブログです。
年金収入の場合、給与収入よりも非課税になりやすいしくみになっています。
今回は、「年金受給者が住民税非課税となる、年収・所得の条件」について紹介します。
【本記事の内容】
① 年金受給者が住民税非課税となる、年収・所得の条件【年金・給与・副業】
② 住民税非課税世帯になるには【単身者と配偶者あり・扶養家族の違い】
③ まとめ:年金収入は控除額が大きく、住民税非課税世帯になりやすいメリットあり
2025年から、"年収の壁" も変わってきています。
年金+労働収入などでの非課税条件も、わかりやすく語っていきます。
① 年金受給者が住民税非課税となる、年収・所得の条件【年金・給与・副業】

① 年金受給者が住民税非課税となる、年収・所得の条件【年金・給与・副業】
低所得と見なされ政府の給付金の対象となる「住民税非課税世帯」になるには、一定基準以下の年収・所得であることが条件です。
会社員やパート・アルバイトなど給与所得者は、"年収110万円以下" だと住民税が非課税になります。(2025年度から10万円引き上げ)
「じゃあ年金収入も年収110万円以下で非課税になるの?」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。
年金収入がある場合にどのくらいの年収だと非課税になるのか、詳しくみていきましょう。
なお、住民税は "前年の収入・所得" から計算される「後払い方式」のしくみです。
2025年度の住民税は "2024年の収入・所得" から計算されたものなので、その点には注意してくださいね。
【年金収入がある場合、住民税非課税となる年収・所得】
❶ 年金収入のみ : 年収155万円以下
❷ 年金収入+給与収入 : 合計所得45万円以下【給与収入10万円引き上げ】
❸ 年金収入+副業収入 : 合計所得45万円以下
年金収入だけの場合と、パート・アルバイトでの給与収入やフリーで稼ぐ副業収入など複数の収入がある場合で変わります。
3つのパターンについて、順番に解説していきます。
【住民税非課税となる市区町村の "級地" による年収条件の違い】
住民税が非課税となる年収条件は、あなたが住んでいる市区町村の "級地制度" によって3段階で区分されています。
・1級地(大都市): 東京23区、横浜市、大阪市など
・2級地(中核都市): あきる野市、海老名市、泉佐野市など
・3級地(上記以外): 奥多摩町、清川村、豊能町など
本記事では1級地の年収で説明していますが、非課税となる年収条件が「2級地・3級地」の場合はそれぞれ "3.5万円・7万円" ほど下がるので、注意してくださいね。
❶ 年金収入のみ : 年収155万円以下
・前年の収入が年金収入のみの場合、年収155万円以下で非課税となる
・「所得 = 収入(155万円) - 公的年金等控除(110万円)」のため、所得でみると45万円以下
・繰り上げ受給で65歳未満の場合は、年収105万円以下に非課税条件が厳しくなる(公的年金等控除額が60万円に下がるため)
前年の収入が「年金収入だけ」の人は、「年収155万円以下」で住民税は非課税となります。
基本的に住民税は "所得" から計算されますが、所得とは「収入から経費を引いた額」のことです。
年金収入による経費は "公的年金等控除" と呼ばれ、収入額と年齢に応じて一律に決められています。
所得でみると「45万円以下」が非課税となる条件ですが、公的年金等控除が "110万円" のため、155万円 - 110万円 = 45万円となるわけです。
なお、65歳未満で年金の繰上げ受給中の場合は、公的年金等控除が "60万円" となります。
控除額が65歳以上の人よりも50万円ほど下がるため、非課税となる年収条件が105万円以下と厳しくなるので、その点は注意しておきましょう。
❷ 年金収入+給与収入 : 合計所得45万円以下【給与収入10万円引き上げ】
・前年の収入が年金収入と給与収入(パート・アルバイトなど)がある場合、合計所得が45万円以下で非課税となる
・年金収入の所得 = 年金収入 - 公的年金等控除(110万円)
・給与収入の所得 = 給与収入 - 給与所得控除(65万円)
・2025年から給与所得控除が「55万円 → 65万円」となり、10万円引き上げに
2つ目は少しややこしくなりますが、「年金収入」と「給与収入(パート・アルバイトなど)」の複数の収入が混ざっている場合です。
このケースでは合計所得が "45万円以下" なら、住民税が非課税となります。
年金収入から所得額を計算するには、年金収入から「110万円(公的年金等控除)」を引けばOKです。
給与収入から所得額を計算するには、給与収入から「65万円(給与所得控除)」を引いて計算しましょう。
例えば、年金収入が130万円なら年金所得20万円(130万円 - 110万円)、給与収入が85万円なら給与所得20万円(85万円 - 65万円)となり、年収は215万円ですが合計所得は40万円です。
所得45万円以下なので、住民税が非課税となる年収条件を満たしています。
-

-
【2025年改正】住民税非課税の年収条件が引き上げ【110万円の壁】
お悩み相談2025年から、住民税非課税世帯になる年収の条件が変わってるの? こんにちは、キベリンブログです。 2025年から "年収の壁" が変わり、住民税非課税世帯の年収 ...
続きを見る
❸ 年金収入+副業収入 : 合計所得45万円以下
・前年の収入が年金収入と副業収入(ブログやYouTubeなど)がある場合、合計所得が45万円以下で非課税となる
・年金収入の所得 = 年金収入 - 公的年金等控除(110万円)
・副業収入の所得 = 給与収入 - 経費(収入を得るために使った費用)
最後の3つ目は、「年金収入」と「副業収入(ブログ・YouTubeなど)」の収入がある場合です。
副業収入にあたるのは会社に雇用されてもらう給料ではなく、個人としてフリーで稼いだ場合の収入ですね。
このケースも2つ目のパターンと同じく、合計の所得が "45万円以下" なら、住民税が非課税となります。
ただし副業収入での経費は、給与所得控除と違って一律に決まっておらず、人によって経費の額は大きく変わります。
年金収入から所得額を計算するには、年金収入から110万円(公的年金等控除)を引けばOKです。
副業収入から所得額を計算するには、副業収入から経費(あなた自身が収入を得るために使った費用)を引いて計算しましょう。
② 住民税非課税世帯になるには【単身者と配偶者あり・扶養家族の違い】

② 住民税非課税世帯になるには【単身者と配偶者あり・扶養家族の違い】
ここまで、年金収入がある場合での住民税が非課税になる年収・所得の条件を見てきました。
政府が給付金を支給するときは、「住民税非課税世帯」を対象にすることが多いです。
いわゆる "個人" ではなく、"世帯" に支給されています。
住民税非課税世帯になると、給付金の支給だけでなく、健康保険料が安くなるといったメリットもあります。
そこで、住民税非課税世帯になるにはどんな条件があるのか、さらに掘り下げて見ていきましょう。
【住民税非課税世帯になるには】
条件❶ : 同じ世帯にいる全員すべての住民税が、非課税であること
条件❷ : 配偶者や扶養家族の人数に応じた所得額の基準よりも少ないこと
上記の2つの条件をともに満たしていれば、住民税非課税世帯になります。
それぞれ説明していきますね。
条件❶ : 同じ世帯にいる全員すべての住民税が、非課税であること
夫や妻、子どもなどと "生計を一にする(生活費が同じ)" 場合、住民票を同一にしていますよね。
同じ住民票に入っている「全員すべての住民税が0円」の場合のみ、住民税非課税世帯になります。
あなた自身に収入がなくても、一緒に暮らしている配偶者(夫 or 妻)や子どものうち誰かひとりでも住民税を払っている場合は、住民税非課税世帯にはなりません。
世帯全員が「住民税 0円」でなければならないので、注意しておきましょう。
なお、単身で扶養する家族もいない場合は、あなた自身の住民税が0円なら「住民税非課税世帯」になります。
一人暮らしでも「世帯」の扱いになるので、前のパートで紹介した年収・所得の条件さえ満たせばOKですよ。
条件❷ : 配偶者や扶養家族の人数に応じた所得額の基準よりも少ないこと
・単身者 : 所得45万円以下(年金収入155万円以下)
・配偶者あり : 所得101万円以下(年金収入211万円以下)
・配偶者+子1人 : 所得136万円以下(年金収入246万円以下)
※単身者以外の所得額の基準は、「(本人+配偶者+扶養親族数)× 35万円 + 31万円以下」で計算される
単身者が住民税非課税になる条件は、「所得45万円以下(年金収入のみで155万円以下)」です。
ですが配偶者や子どもなど扶養親族がいると、人数が増えるほど所得の上限も大きくなっていきます。
配偶者や扶養親族がいる場合、住民税が0円になる所得の上限は、「(本人+配偶者+扶養親族数)× 35万円 + 31万円以下」で計算されます。
例えば「配偶者あり(子なし)」の場合は「所得101万円以下」で、「配偶者+子1人」なら「所得136万円以下」ですね。
所得額は、前のパートで紹介した3つのパターンから計算できます。
年金収入や給与収入など、あてはめて計算してみてください。
-

-
住民税非課税世帯が優遇される、7つのメリット【年収の目安】
お悩み相談"住民税非課税世帯" ってよく聞くけど、どんなメリットがあるの? こんにちは、キベリンブログです。 税金はしくみがややこしくて、非課税のメリットもあまり知られてい ...
続きを見る
③ まとめ:年金収入は控除額が大きく、住民税非課税世帯になりやすいメリットあり

③ まとめ:年金収入は控除額が大きく、住民税非課税世帯になりやすいメリットあり
本記事では、「年金受給者が住民税非課税となる、年収・所得の条件」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【年金収入がある場合、住民税非課税となる年収・所得】
❶ 年金収入のみ : 年収155万円以下
❷ 年金収入+給与収入 : 合計所得45万円以下【給与収入10万円引き上げ】
❸ 年金収入+副業収入 : 合計所得45万円以下
【住民税非課税世帯になるには】
条件❶ : 同じ世帯にいる全員すべての住民税が、非課税であること
条件❷ : 配偶者や扶養家族の人数に応じた所得額の基準よりも少ないこと
"住民税非課税世帯" と一口に言われても、どんな人が対象になるのか分かりにくいのが実情です。
住民税は1年遅れの後払い方式のしくみで、「前年の所得」から決まります。
年金収入だけの場合は、"年収155万円以下" なら住民税は非課税となります。
年金に加えて給与収入や副業収入がある場合は、所得の計算が必要なので、本記事を参考に45万円以下になるか計算してみてください。
給付金の支給は「住民税非課税世帯」が対象となることが多いので、個人ではなく "世帯" で見るポイントも重要です。
年金収入は控除額が大きいので、収入と所得の違いには気をつけてくださいね。
-

-
年金繰り上げ受給で、得する人・損する人【メリットと選び方】
お悩み相談年金制度は今後不安だし、早めにもらっておきたいよね。 繰り上げ受給したいけど、やっぱり損するのかな? こんにちは、キベリンブログです。 年金の繰上げ受給したくても ...
続きを見る
-

-
【要申請】年金生活者支援給付金で、6.5万円の上乗せ支給!
お悩み相談年金収入だけだと、物価も上がってるし生活厳しいなぁ...。 え、年金に上乗せでもらえる給付金があるの!? こんにちは、キベリンブログです。 厚生年金の加入期間が短 ...
続きを見る
-

-
【2025年改正】住民税非課税の年収条件が引き上げ【110万円の壁】
お悩み相談2025年から、住民税非課税世帯になる年収の条件が変わってるの? こんにちは、キベリンブログです。 2025年から "年収の壁" が変わり、住民税非課税世帯の年収 ...
続きを見る