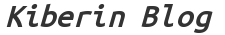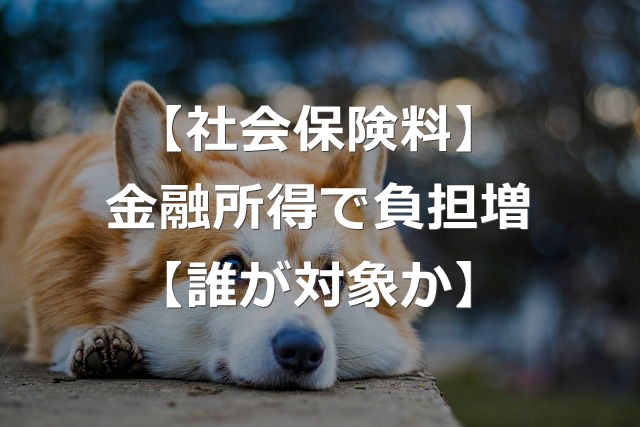リスクを取って資産運用してるのに...。
こんにちは、キベリンブログです。
政府が株式配当などの金融所得を、医療や介護の保険料額に反映する検討を進めています。
今回は、「金融所得の社会保険料への反映で、現役世代も負担増になるのか」について紹介します。
【本記事の内容】
① 金融所得を社会保険料に反映させる狙いと背景【高齢者の富裕層】
② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代の負担は増えるのか【今後の可能性】
③ まとめ:金融所得による社会保険料の負担増は、まずは高齢者が対象
新NISAで投資が広がる中、新たな負担増を狙っています。
社会保険料にどう影響していくのか、わかりやすく紹介していきます。
① 金融所得を社会保険料に反映させる狙いと背景【高齢者の富裕層】

① 金融所得を社会保険料に反映させる狙いと背景【高齢者の富裕層】
2025年7月、「金融所得、医療や介護保険料に反映検討 SNSで広がる誤解・懸念」という記事が報道されました。
金融所得(株の配当金や売買で得た収益)も社会保険料の計算に入れて、保険料を値上げしようという狙いです。
少子高齢化で社会保険は財源が厳しく、あらゆるところから取ることを検討しています。
現状のしくみも踏まえつつ、今後どう変わっていくのか見ていきましょう。
"医療・介護保険の負担への金融所得の反映に向け、制度設計を進める" ことを閣議決定
医療・介護保険における負担への金融所得の反映に向けて、税制における金融所得に係る法定調書の現状も踏まえつつ、マイナンバーの記載や情報提出のオンライン化等の課題、負担の公平性、関係者の事務負担等に留意しながら、具体的な制度設計を進める。
(経済財政運営と改革の基本方針2025 から引用)
政府が2025年6月13日にまとめた閣議決定の資料によると、上記の内容が明記されています。
金融所得の課税に対する増税は、これまでも何度が話題になりました。
今回の閣議決定は、"金融所得で社会保険料(健康保険料)も負担させていこう" という内容です。
そもそも現状のしくみはどうなっているのか、チェックしていきますね。
金融所得の社会保険料への反映【現状のしくみ】
・確定申告した場合 : 社会保険料に反映される
・確定申告しなかった場合 : 社会保険料に反映されない
※特定口座で株を運用している人は、確定申告をするかどうか選べる
現状の金融所得による社会保険料のしくみは、上記のとおり「確定申告の有無」によって、反映されるかが変わってきます。
多くの人は株の運用を "特定口座" と "NISA口座(非課税)" で行っていますが、特定口座では確定申告しなくてもOKで、確定申告するかを個人で選ぶことができます。
確定申告した場合は、現状でも社会保険料に反映されており、金融所得で得た収益の分だけ負担は増えています。
一方で確定申告しなかった場合は、約20%の税金が源泉徴収されるだけで、現状では社会保険料には反映されていません。
個人の選び方で社会保険料に差があるのは、"公平性" に欠けている見方があります。
そのため、「確定申告しない場合でも、社会保険料の計算に反映させて負担を増やそう」という狙いです。
金融所得を社会保険料に反映する案が出てきた背景
・後期高齢者(75歳以上)の医療費の4割は現役世代が負担しており、負担が大きい
・高齢者の医療費は現役世代の4倍以上であるが、高齢者の金融資産は減っていない
・金融資産を持っているのは高齢者が多いことから、金融所得も社会保険料に反映させることを提案
なぜ金融所得を社会保険料に反映させる案が出てきたかというと、医療費の負担状況にあります。
少子高齢化の加速で、現役世代の負担は増え続ける一方です。
医療費の大部分は高齢者が使っているわけですが、政府の統計データ上では高齢者の金融資産は減っていません。
そこで、「高齢者も保険料を負担すべき」との案が生まれてきました。
株の保有率に目を向けると、"70代以上" が「全体の4割」の株を持っています。
株の収入を含む金融所得で社会保険料(医療・介護保険料)を値上げすれば、高齢者の保険料負担につながるということですね。
こうした背景を踏まえた上で、冒頭で紹介した「SNSで広がる誤解・懸念」について次のパートで見ていきましょう。
現役世代の負担はさらに増えるのか、考察していきます。
② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代の負担は増えるのか【今後の可能性】

② 金融所得の社会保険料への反映で、現役世代の負担は増えるのか【今後の可能性】
ここまで、金融所得の社会保険料への反映について紹介してきました。
冒頭で紹介した記事にあるSNSで広がる "誤解・懸念" というのは、「現役世代の社会保険料の負担が、さらに増えるのではないか?」ということ。
NISA導入で投資を勧めておきながら、課税の負担を重くすることは、逆向する流れとも言えます。
今後どのように金融所得が社会保険料に反映されるのか、見ていきましょう。
金融所得による社会保険料負担の対象は、まずは高齢者から
そもそもこの話が出てきたのは、「現役世代の社会保険料の負担が重すぎる」ということが背景にあります。
"給料の30%(会社との合計額)" もの金額が、社会保険料で取られています。
そのため、まずは「後期高齢者(75歳以上)」が金融所得での社会保険料(医療・介護保険料)を負担することが想定されています。
段階的に年齢を下げていき、次は65歳以上の高齢者が対象になる見込みです。
ただし、「NISA口座」での運用益については、社会保険料には反映させないとしています。
なので特定口座を使わず、NISA口座のみで株や投資信託を運用しているなら、当面は負担増になることはなさそうです。
現役世代への負担増は、本当に誤解?【会社員は仕組み上難しい】
現役世代が金融所得で社会保険料の負担が増えることは、すぐには発生しないと思います。
なぜなら、現役世代の多くの人は会社員であり、健康保険料の金額は "給料" から計算されているからですね。
仮に実現しようとすると、会社(健康保険組合)が各個人の金融所得を把握しなければなりません。
現状はその仕組みがないので、制度設計が難しく、ややハードルが高いです。
一方で、年金生活者や自営業・フリーランスが入る国民健康保険(75歳以上は後期高齢者医療)は、証券会社が税務署に通知している金融所得(特定口座の年間取引報告書)の情報を市区町村にも通知するだけで、すぐに実現が可能です。
なので最初のターゲットとしては、国民健康保険への加入者が多い後期高齢者からになると思われます。
金融所得はマイナンバーと紐づいており、ゆくゆくは全世代負担の可能性も
"当面" は、金融所得による社会保険料への反映で、現役世代の負担が増えるというのは "誤解" と言えるかもしれません。
ですが、金融所得の情報は、すでにマイナンバーと紐づいている状態です。
証券口座を持っているなら分かると思いますが、口座の開設にはマイナンバーの提出が求められていますよね。
やろうと思えば、マイナンバーを使って世代を問わず金融所得を社会保険料に反映させることも可能です。
政府内の会議では、「金融所得があるなら、世代に関係なく公平に取るべき」との発言も出ています。
もし高齢者から金融所得の社会保険料への反映が開始されたら、ゆくゆくは年齢に関係なく、全世代が負担する流れになりそうですね。
③ まとめ:金融所得による社会保険料の負担増は、まずは高齢者が対象

③ まとめ:金融所得による社会保険料の負担増は、まずは高齢者が対象
本記事では、「金融所得の社会保険料への反映で、現役世代も負担増になるのか」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【金融所得の社会保険料への反映(現状のしくみ)】
・確定申告した場合 : 社会保険料に反映される
・確定申告しなかった場合 : 社会保険料に反映されない
※特定口座で株を運用している人は、確定申告をするかどうか選べる
【金融所得を社会保険料に反映する案が出てきた背景】
・後期高齢者(75歳以上)の医療費の4割は現役世代が負担しており、負担が大きい
・高齢者の医療費は現役世代の4倍以上であるが、高齢者の金融資産は減っていない
・金融資産を持っているのは高齢者が多いことから、金融所得も社会保険料に反映させることを提案
株の譲渡益や配当金などの金融所得を社会保険料に反映させる案は、今後制度設計が進められていきます。
政府の資料を見る限りでは、まずは高齢者が対象になりそうです。
当面は現役世代の負担が金融所得によって増えることは "誤解" と思われますが、ゆくゆくは分かりません。
いったん制度が導入されたら、「75歳以上 → 65歳以上 → ・・・」と徐々に対象が引き下げられる可能性が高そうです。
なお、NISA口座での金融所得は、社会保険料には反映されないとしています。
リスクを取って運用している金融所得の社会保険料への反映は納得できないところもありますが、増税は避けられない流れなので、今後の情報に注意しておきましょう。
-

-
【NISAどうなる】金融所得課税、20%→30%増税か【FIRE危機】
お悩み相談金融所得課税の増税って、株の収入とかから引かれるんだよね? せっかく投資を始めたのに、NISAはどうなるの!? こんにちは、キベリンブログです。 "手取りを増やす ...
続きを見る
-

-
【2025年改正】住民税非課税の年収条件が引き上げ【110万円の壁】
お悩み相談2025年から、住民税非課税世帯になる年収の条件が変わってるの? こんにちは、キベリンブログです。 2025年から "年収の壁" が変わり、住民税非課税世帯の年収 ...
続きを見る
-

-
【社会保険料】ダブルワーク・副業で安くなる?残業より稼げる理由
お悩み相談副業とかダブルワークするときって、社会保険料はどうなるの? 高くなったりするのかな?? こんにちは、キベリンブログです。 複数から収入がある場合、社会保険料のしく ...
続きを見る